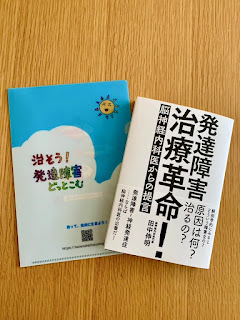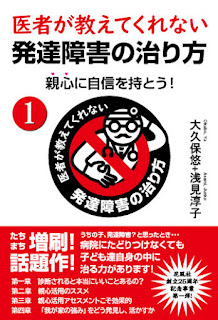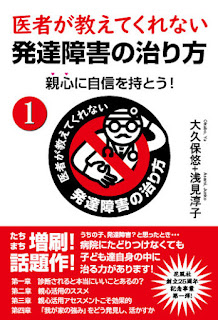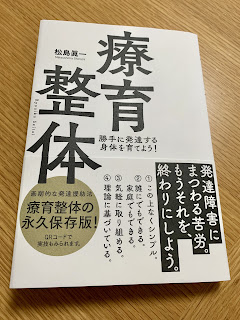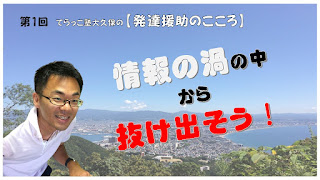【No.1392】焼け野原になった2023年から2024年に向けて
上の子が「お父さんのYouTube、バズってるよ!」と教えてくれた。 よくわからないれど、学校の休み時間に個人用のタブレットで毎日、チェックしているらしい(笑) 息子世代のYouTubeに対する捉え方は私とは違うようで、登録者数がどうのこうのとか、もっとこうしたらバズるんじゃないかとか、誰々を真似したらもっとPVが増えるとか、興奮気味に話してくる。 ちなみになんの動画がバズったのかと言えば、 【コロナ社会の影響】こんな赤ちゃんが増えました です。 この動画は私が発達相談を通して見聞きしたことや現場の保育士さん達から聞いた話を動画にしているのですが、どういうわけか12月に入っての短期間で視聴回数が増えたのです。 今で約6.7万再生。 コメント数もびっくりするくらいあって、数件批判的なコメントがあったものの、ほとんどの人が「やっぱり枠の影響では」「子ども達のことが心配」「実は知り合いのおうちでも」など、共感してくれるものばかりでした。 「薬害エイズのときも、3年経つと風向きが変わった」という話がありましたので、やっぱり多くの人が気付き、声を上げるようになるまでは3年という期間が必要だったのかもしれません。 いずれにしましても、今年は「変わり目」の年であり、「入れ替えの年」だったんだと思います。 てらっこ塾を始めて丸10年の節目の年で、ちょうどYouTubeでの配信を始めてから、それまでのお客さんからガラッと雰囲気が変わった気がします。 それまで支持してくれていた人が去り、新しい親御さんが応援してくれるようになった、そんな感じです。 それが象徴されるのが、発達相談の依頼のメールやお会いする親御さん達がおっしゃる言葉で、端的に言えば「私がこの子の発達の遅れに影響をしていると思う。だから、私自身の課題を克服していきたいので、発達相談をお願いします」というものです。 それまでは「この子の課題を」「発達のヌケをアセスメントして欲しい」「どうすれば未発達が育つのかアプローチを教えて欲しい」という感じでしたから。 なんで、今年の発達相談はとても充実していました、個人的に。 だって、本気度が違うんですもの。 そして何よりも、発達相談後の変化、改善が著しい。 そりゃそうですよね、より根っこ、根本に向き合うのですから。 発達の遅れ、発達障害と言われる状態は結果であって、原因ではありません。