【No.1257】関係性で表れる"発達の遅れ"という現象
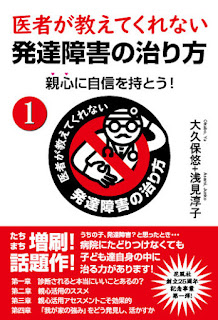
先日、おばあちゃんから孫と娘夫婦のことで相談がありました。 言葉が出ない孫に対して、娘が発達障害ではないか、きっとそうだと思い込み、パニックになっていると。 ですから私は勝手に3歳くらいのお子さんかなと思ったのですが、お孫さんの年齢を聞けば、まだ1歳半とのこと。 ネットで調べれば、ほとんどの子どもさんが1歳半の時点で初語が見られるという記事が出てきますが、だからといってすぐに発達障害になるわけでも、今後一切言葉がでないわけでもないと思います。 そのおばあちゃんも言っていたのですが、昔は小学校でもしゃべれない子がいた、と。 そういった子も、気がついたら話ができるようになっているもので、私が知っているだけでも小学校以降、言葉が出るようになった人は何名もいますね。 娘はネットで調べたことばかりで聞く耳を持ってくれないとおっしゃっていましたが、その根っこはおばあちゃんと娘との関係性の中にあるように感じました。 発達の遅れは、観察できるモノではありません。 それは現象であって、様々な出来事との関係性の中で表れているのだといえます。 つまり、発達の遅れというモノが存在しているのではなく、今この瞬間の姿でしかないのです。 しかし現実はその観察できる姿、いや、本人ではない他人が観察した姿を発達障害とラベリングしています。 その子に表れた発達の遅れは、環境(家庭、園や学校、周囲の自然、栄養、遊びなど)と、過去の出来事(胎児期からの体験、ヌケ、健康状態)、遺伝(三世代で引き継がれる資質)の関係性から見ていかないと、その輪郭は掴めないものです。 同じ言葉の遅れにしろ、お父さんが小学校高学年までほとんどしゃべらなかったとしたら、お子さんも同じくらいの時期までしゃべらない可能性が高いでしょうし、運動発達にヌケが多くあれば言葉の発達まで進まないこともあり、言葉を獲得する前の長時間のメディア視聴は言葉の発達を阻害します。 とてもシンプルに言っても、このように環境、過去の出来事、遺伝でそれぞれ遅れを生む要因はありますし、実際は様々な要因が複雑に関係し合い、またそれゆえに個別的な事象となるわけです。 本来、このように確認していかなければわからないものですが、今行われている診断はこのような仕組みにはなっていません。 もちろん、市町村が行っている健診の保健師さん達も、そこまで詳しく確認してませんし、親御...





