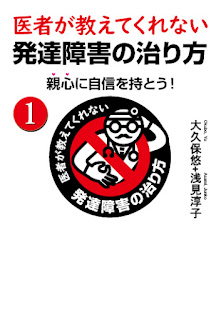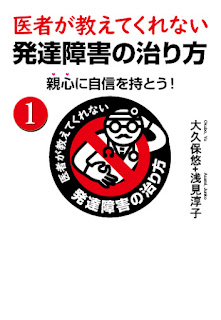【No.1215】2021年暮れのご挨拶

大晦日の函館は、最高気温がマイナス7℃という素敵な数字を叩き出しました。 ジムに行くのも寒いし、帰ってくるのも寒い。 お礼参りも激さむでした そんな中で今、やっと雪かきが終わり、パソコンの前に座っております。 2021年を振り返ると、まさか呼んでくださるとは思わなかった沖縄のご家族からの出張の依頼がありました。 何度も「よろしいんですか?」「私は北海道ですよ」「2000キロくらい離れていますよ」「台湾、中国のほうが近いですよ(笑)」「函館からはロシアのほうが近いですよ(笑)」とお尋ねし、「それでも」というお話でしたので伺いました。 親御さんの想いは、南国の陽射しよりも熱かったですね。 他にも、福岡、広島、関東はほぼ毎月でちょくちょく、今年は道内も結構回りました。 たまたまではありますが、札幌出張とオリンピック競歩の日が重なり、目の前でオリンピアンの競技する姿を見られたことはよい思い出になりました。 18歳のとき、初めて手にした障害系の本が花風社さんの『自閉っ子、こういう風にできています!』でした。 それから20年ほど経ち、花風社さんの25周年記念事業の『医者が教えてくれない発達障害の治り方』の出版に携わらせていただきました。 共同著者としてこの世に本が出たことは私にとって嬉しいことではありましたが、私以上に周りの人達が喜んでいることにびっくりしました。 妻、息子たち、両親はもちろんのこと、てらっこ塾を始めたときに応援してくださった方たち、利用したことがある親御さん達、今利用している親御さん達、そして自分自身で治していき、自分の人生を歩まれている若者たち、お子さん達。 函館蔦屋書店で開催させていただいた出版記念イベントにも、懐かしい方たちも来てくださり、さらに大きく成長した姿を見せてくれました。 また「本、買ったよ!」と連絡をくれた方たちもいました。 出張の依頼と同じように、出版というお仕事も社会に求められた結果だと思っています。 私自身、まだまだ反省ばかりで、もっとアセスメントの力を磨かねば、もっと親御さんが前向きになるような後押しを、もっといろんなアイディアが浮かんでくるようなヒントを、もっと子育てが楽しいと思ってくれるような話を、と思い続ける日々です。 ただ今回、出版のお声がけがあったのは、私のように全国各地に出向き、しかも家庭の中に入っての発達相談をやっている...