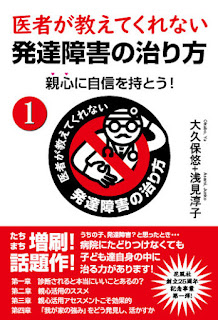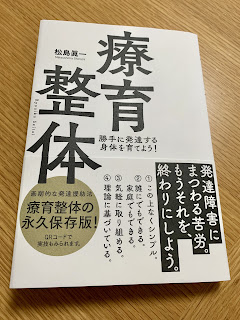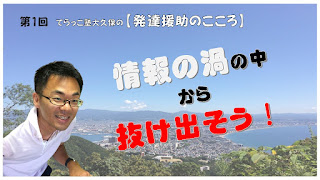【No.1367】おススメ動画に出てくる涙ぐむママたちを見て
ユーチューバーになってからというもの、やたらとおススメに発達障害を持つママの動画が流れてきます。 もちろん、今までもそうやって動画をあげてる親御さんがいるのは知っていたけれども、まったく観る気が起きなかった。 だって邪気に溢れているでしょ(笑) それに勝手に「私は障害者として生きます」宣言がよりによって親にされちゃっている子が不憫で仕方がないから。 でもいくつかの動画を観てみました。 そこで気が付いたのは、編集が上手ってこと(笑) つまり、どんなフラクタル構造化と言えば、現実も編集したいという想いなんですね。 私が見た限りですが、全員、我が子の発達の遅れを受け止めることができていない、そして根本から変わっていくことを諦めている。 別に現時点で遅れているからっていって、1年後も、2年後も、遅れ続けているかはわからないのにね。 だけれども、「遅れ=生涯変わらないモノ」なっているから、編集に「変わるものなら変わりたい」「あのときのあの選択をやめたい」という願望を乗せている。 また編集って「見せたいところを見せる」と同時に、「見せたくないところは見せない」なんですね。 これまたフラクタル構造の「表面に目を向け根本を見ない(見れない)」「自分が見たくないところは見ない(=自分は悪くないと思いたい)」が出ている。 どの子も重度と言うけど、脳のダメージは見えないし、「やれば、本来の発達の流れに戻るよな」って感じ。 でも根本に向き合えないご家庭は(本人の問題じゃなくて)治るのは無理だよな~と思う。 まあ、またまたフラクタル構造で、世の中、こんなご家庭ばっかりで治したくない、治ってほしくない親御さんが大多数なのでしょう。 私が「根本」「根本」というのは、治っていかない、本来の発達の流れに戻っていけない、という理由もあるけれど、根っこという土台の部分が治らなきゃ、結局のところ、発達の凸凹が大きくなって新たな生きづらさが生まれるし、人生で出くわす困難がやってきて倒れたあと、ぽきっと折れちゃって立ち上がれない元発達障害児たちを見てきたから。 そして何よりも、次の世代に影響が出ちゃうでしょ。 まあ、頑張れば、対症療法だけで、〇〇アプローチだけで治る子、元の流れに戻る子はいる。 だけれども、「どうして発達が遅れたのか?」「どうして発達が遅れたままなのか、そこから育っていかなかったのか?」がわか...