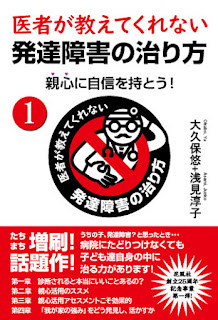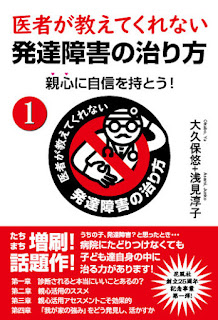【No.1320】安心は発達のエネルギー

前回のブログ に対して反響が多くありました。 ホントはこういうことを書くと、ますます怪しさが増すから避けてきていたんですよね(笑) でも、書かざるを得なかった、というのが正直な気持ち。 だってええ、発達障害が発達の問題"だけ"だと思っている人が多いんですもの。 発達障害を治そうとするその行為が却って、愛着障害を生み、更なる発達の遅れに繋がっていることがあるんですもの。 「我が子の発達障害を治すにはどうしたら良いですか?」という質問が出ること自体、治っていけない家庭の典型だといえます。 発達相談でご家庭に伺うと、親御さんの深刻さを横に、子どもさんが幸せそうに遊んでいる姿がある、ってことはよくあることです。 親御さんからしたら発達の遅れやその指摘は、奈落の底に落とされた感じになるのは当然だと思いますが、子どもさんはそのことについてどう思っているのでしょうか? もちろん、ある程度大きくなり、また他人との違いを感じるような年代になれば、「治りたい」と本人が願うこともあるでしょう。 しかし最近増え続ける乳幼児さんの発達相談、小学校低学年くらいまでの子ども達は、どのくらいそれを思っているのか。 本当に今、いろんなものを後回しにして、もっといえば、家族の時間、親御さんとの触れ合いや甘え、子ども時代の自由な時間を後回しにして、その療育に通うことは、診断を受けに行くことは、薬を飲むことは、そのアプローチを行うことは、発達障害を治そうとすることはやるべきことなのか、と思うことがあるのです。 先日、お会いした子どもさんは、「もっとお母さんと遊びたい」と言っていました。 親御さんとしては、一刻も早く治ってほしい、今すぐにでもラクになってほしい、と願う。 だけれども、子どもからしたら今、お母さんと遊びたいんですね。 もっと抱きしめて欲しいし、ただただ自分だけのことを見てほしい。 そもそもが発達が遅れていること自体を、その子は不幸に感じていない。 特に子どもは敏感に親御さんの想いを感じるもので、親御さんが発達の遅れに対してネガティブな感情を持ち続けると、それを感じた子が「自分ってダメな子なんだ」と捉えてしまうこともありますね。 子どもさんの発達の遅れに注目が集まるようになってから、「発達が(さらに)遅れ出す」なんてことも少なくありません。 本当にそれが発達の遅れなのか、単に...